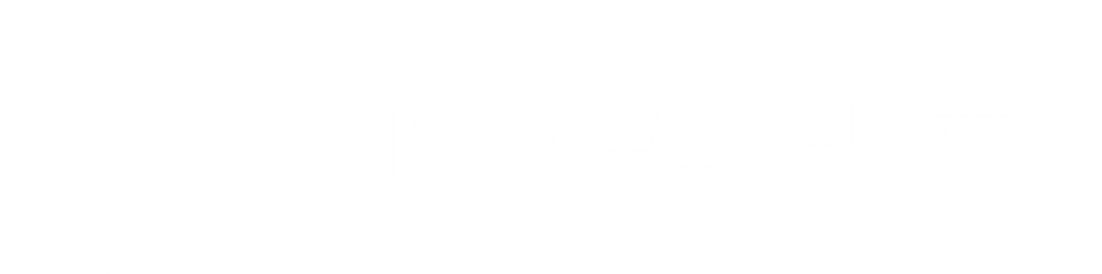代表理事挨拶
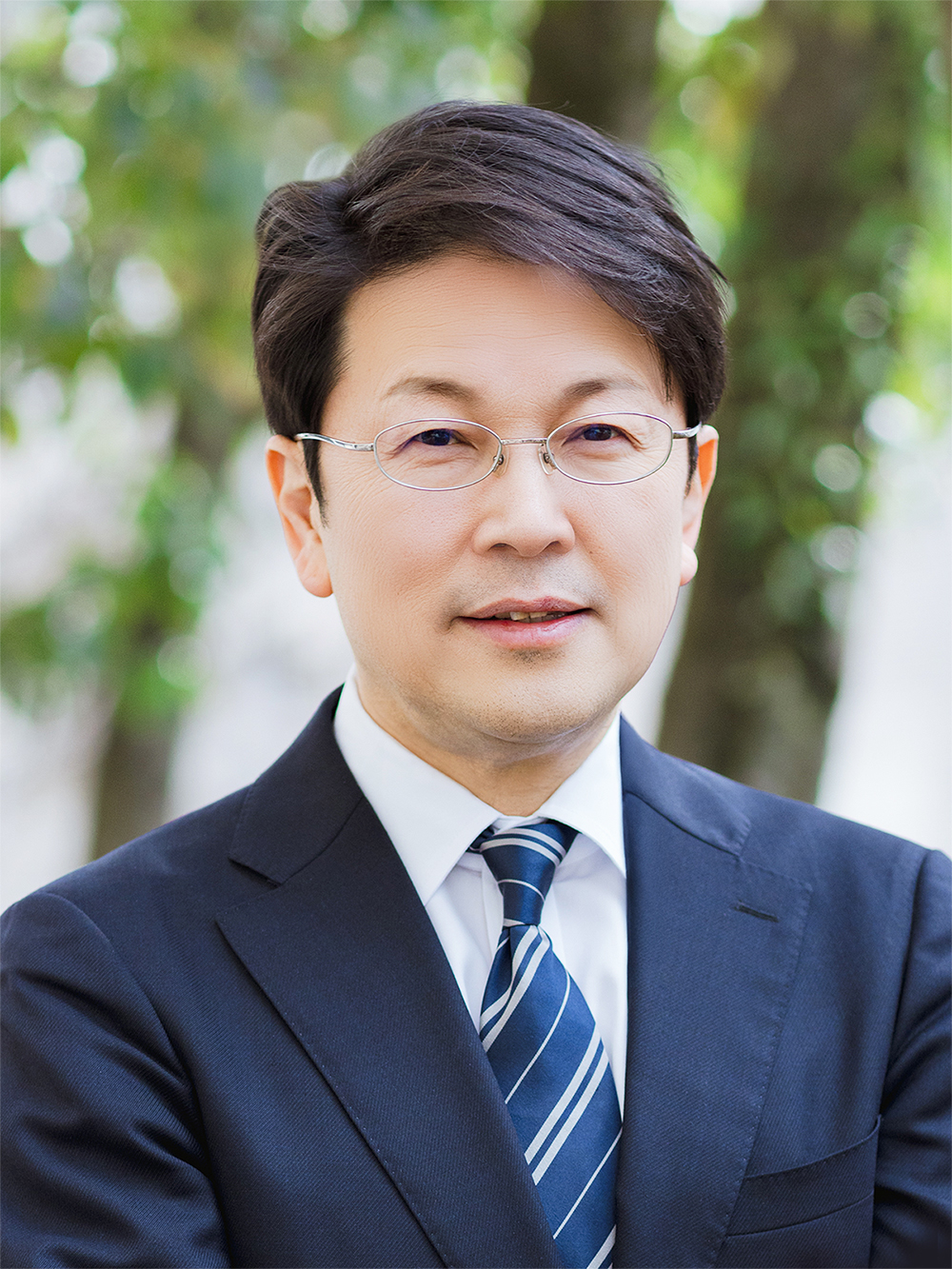
代表理事 井上治久
幹細胞は、分化した体細胞とは異なり、特定の細胞系譜へと分化する能力と自己複製能を併せ持つ細胞です。その中でも、あらゆる細胞種へ分化可能な多能性幹細胞(ES細胞・iPS細胞)と、組織特異的に機能する体性幹細胞の両者が存在し、それぞれが異なる文脈で生体理解や医療応用に貢献してきました。
ES細胞は1981年に、iPS細胞は2006年に初めて樹立されました。一方で体性幹細胞はより早い段階から、造血幹細胞や腸管・皮膚上皮などを中心に臨床的・基礎的研究が進められてきました。いずれの幹細胞も、当初は細胞移植を主な目的とした再生医療への応用が期待され、機能を回復する細胞源としてその意義が追求されてきました。
しかし近年では、これらの幹細胞を疾患の標的細胞へと分化誘導し、二次元培養系に加えて、オルガノイドとMicrophysiological Systems (MPS)などを用いることで、病態を再現する疾患モデルの構築、病因の解析、薬剤スクリーニングといった新たな応用が急速に拡がっています。とりわけ、患者ご本人から得られた体細胞からiPS細胞を作製し、病気の標的細胞へと分化誘導して病態を直接観察・解析できるようになったことは、21世紀の生命科学におけるブレークスルーのひとつです。こうした技術革新により、個別化医療や新たな治療法開発の可能性が大きく広がっています。
現在、幹細胞研究はさらに大きな飛躍の時代を迎えています。細胞培養・分化誘導技術の高度化、マイクロ環境の精密制御、動物実験代替技術の確立に加え、マイクロ流体工学やMPSを応用した微小デバイス技術の発展により、オルガノイド技術を組み込んだ機能的で再現性の高い生体模倣系の構築が急速に進んでいます。これらは基礎研究と臨床応用の間をつなぐ重要な橋渡しとなっています。
我が国においても、幹細胞研究はゲノム編集、細胞製造、人工知能(AI)解析などの先端分野と融合し、医工薬理情報の枠を超えた学際的連携が加速しています。AIと統合されたiPS細胞モデル・デバイスに加え、オルガノイドを活用したプラットフォームは、創薬効率の向上や疾患メカニズムの多角的理解、精密な遺伝子治療研究に寄与しつつあります。また、発生生物学の観点からもオルガノイドは、ヒト組織の立体的発生過程を再現する強力なツールとして注目されています。こうした研究は高度な専門性と異分野連携を要し、相互理解と知識統合のための継続的な努力が不可欠です。
本学会は、幹細胞生物学、基礎医学、臨床医学、分子生物学、工学、情報科学など多様な専門家が結集し、疾患幹細胞研究のさらなる進歩と社会実装を支える基盤を築くことを目的に設立されました。会員相互の連携を促進し、研究の質を高めるとともに、次世代研究者の育成や社会との対話を重視し、学術コミュニティの発展を目指してまいります。
私たちは、疾患幹細胞研究を通じて生命科学の発展に寄与し、医療の未来を切り拓くことを使命としています。会員の皆様、関係各位におかれましては、本学会の活動に一層のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。